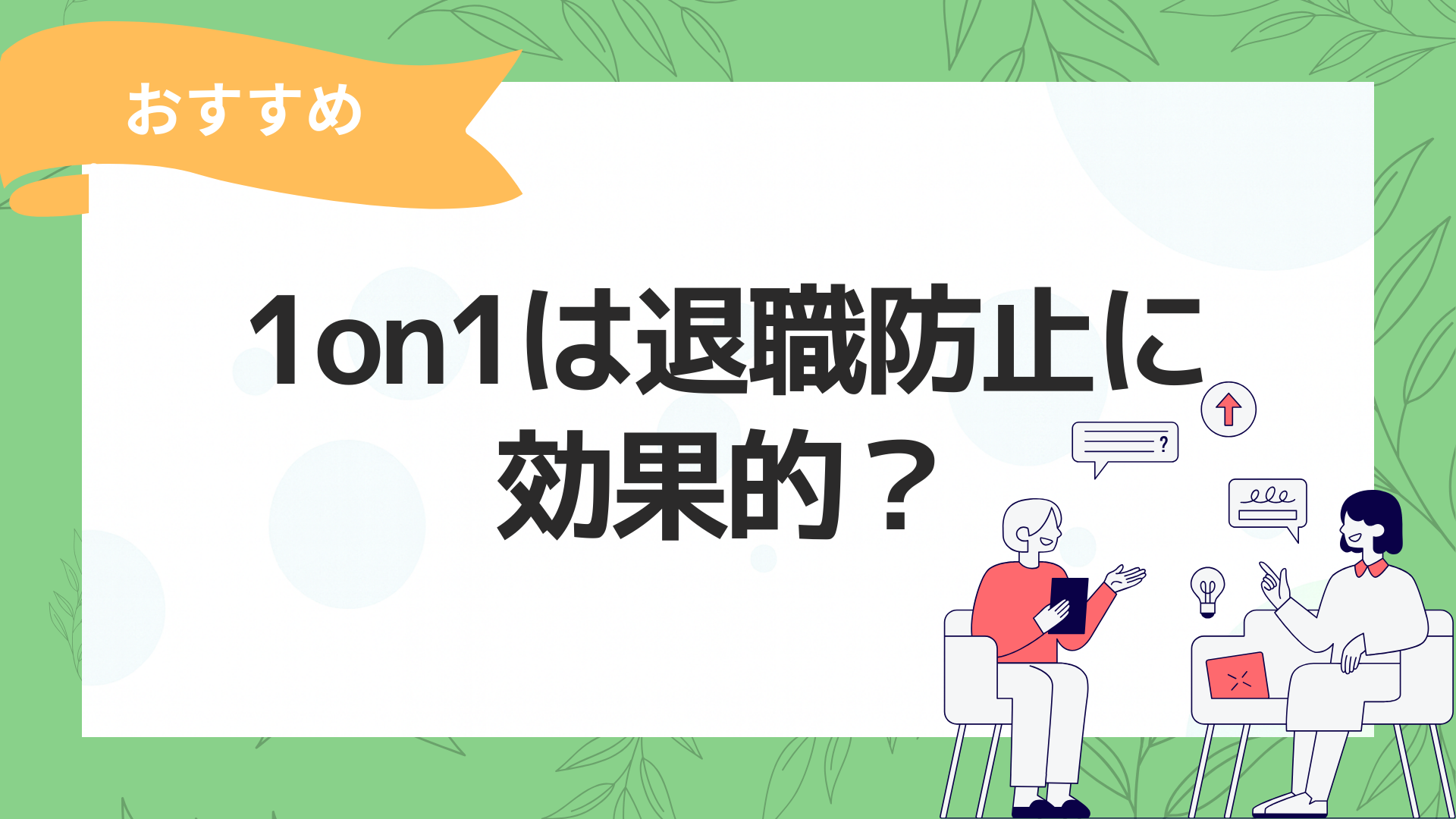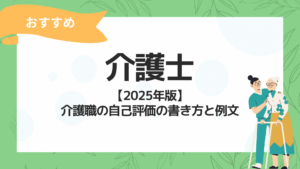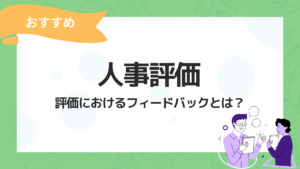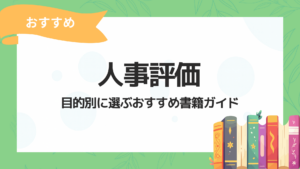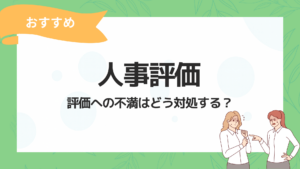なぜ1on1で退職が話題になるのか
今、多くの企業で1on1ミーティングが部下の育成やエンゲージメント向上を目的に利用されています。しかし、その内容次第では退職の意向が突然示される「びっくり退職」や、若手社員の早期離職につながる事例も少なくありません。1on1と退職が関連して語られるのは、このように対話の質が社員の定着に直結するからです。
以下では、突然の退職が起きる理由や若手社員の早期離職の現状、そしてコミュニケーション不足が招くすれ違いについて詳しく解説していきます。
「びっくり退職」とは?突然の離職が起きる背景
「びっくり退職」とは、上司や組織が予期しないタイミングで社員が退職を申し出る現象を指します。表面的には業務に問題がなくても、内心では不満や不安が積み重なっており、それを上司が把握できていないことが原因です。
特に1on1の場は、部下が退職の意向を初めて伝える機会になりやすく、企業にとっては大きなダメージとなります。背景には「普段から不満を話せる環境がない」「上司が部下の変化に気づけない」といった組織課題があります。
びっくり退職を防ぐためには、日常的な信頼関係づくりと早期のサイン察知が欠かせません。
若手社員の早期退職が増える理由
近年では、新入社員や入社数年の若手社員による早期退職が増加しています。その背景には、キャリア形成への期待と現実とのギャップや、評価・育成体制への不満があります。特にZ世代と呼ばれる若手は、自分の成長実感ややりがいを重視する傾向が強いため、上司との1on1でそのニーズが満たされないと「この会社にいても成長できない」と判断しやすいのです。
また、転職市場の活発化により「合わなければ別の環境に行く」という選択肢が現実的になっていることも要因です。1on1は、こうした若手の本音を早期に引き出し、モチベーション低下や退職を未然に防ぐ重要な機会といえます。
コミュニケーション不足が招くすれ違い
退職につながる大きな要因の一つが、上司と部下のコミュニケーション不足です。
業務指示や成果評価に偏ったやり取りでは、部下の悩みやキャリア志向が共有されず、相互理解が深まりません。その結果、上司は「順調に働いている」と認識しているのに、部下は「分かってもらえない」と感じて孤立し、突然の退職につながります。
1on1はこのギャップを埋めるための場であるにもかかわらず、雑談や形だけの面談で終わってしまうと逆効果になりかねません。日常的に信頼関係を築き、1on1を「一方的な評価の場」ではなく「双方向の対話の場」として活用することが、退職防止に直結します。
1on1が退職を防ぐと言われる理由
1on1ミーティングは単なる業務進捗確認ではなく、部下の悩みやキャリア志向を理解する重要な場です。適切に行うことで、部下の本音を引き出し、心理的安全性を確保し、さらには退職の兆しを早期に察知することが可能になります。結果として「びっくり退職」を未然に防ぎ、社員の定着率を高める効果が期待できます。
以下では、1on1が退職防止につながる具体的な理由を解説します。
部下の本音を引き出す機会が増える
日常業務では上司に言いづらい不満や悩みも、1on1の場であれば打ち明けやすくなります。定期的に時間を確保することで「自分の声を聞いてもらえる」という安心感が生まれ、普段は表に出ない本音を引き出せるのです。特に若手社員は、評価や昇進に直結する場ではなくフラットな対話の場を求めています。
そのため1on1では、業務の話だけでなくキャリアの希望や働き方の悩みについて耳を傾けることが重要です。本音を共有する機会が増えることで、不満が深刻化する前に対策が打てるため、突然の退職を防ぐ効果が高まります。
心理的安全性を高めて不満を解消できる
退職理由の多くは、仕事内容そのものよりも「人間関係」や「相談できない環境」に起因します。
1on1は部下が安心して意見を話せる環境を作る絶好の機会であり、心理的安全性を高めることで不満や不安を解消できます。
例えば、失敗や課題を指摘されても「成長のためのサポート」として受け止められれば、部下は萎縮せずに前向きな気持ちを維持できます。逆に心理的安全性が欠如した職場では、部下は悩みを抱え込んでしまい、限界を迎えた時に退職を選択しがちです。1on1を通じて「話しても大丈夫」という信頼関係を築くことが、離職防止の大きなカギになります。
退職の兆し(態度・行動変化)に気づける
社員が退職を考え始めると、小さな行動や態度に変化が現れるものです。
例えば
- 「以前より発言が減った」
- 「残業や休日出勤を避けるようになった」
- 「急な欠勤や遅刻が増えた」等
こういったことは退職のサインといえます。1on1を定期的に行えば、こうした変化にいち早く気づき、早期に対応することができます。さらに1on1では、業務の進め方だけでなく「最近の仕事へのモチベーション」や「今後のキャリア希望」を尋ねることで、退職の意思を持つ前段階の違和感をキャッチできます。早期発見・早期対応ができれば、部下の気持ちを引き留め、離職を未然に防ぐ可能性が高まります。
一方で1on1が退職を後押ししてしまうケース
本来は退職防止の役割を担う1on1ですが、運用を誤ると逆に部下の不信感を強め、離職を加速させる危険もあります。目的を理解せず形式的に行う「やらかし1on1」や、上司の一方的な評価・指導に偏った面談、あるいは雑談だけで課題が放置されるケースでは、部下は「意味のない時間」と感じやすくなります。
ここでは、退職を後押ししてしまう失敗パターンを具体的に見ていきましょう。
目的を理解せず形式的に行う「やらかし1on1」
1on1を導入する企業は増えていますが、形だけを真似て「やっていること自体」に満足してしまうケースは少なくありません。
上司が1on1の本来の目的を理解せず、単なる業務報告や定例チェックのように進めてしまうと、部下は「ただの管理ツール」と感じて不信感を募らせます。こうした「やらかし1on1」は、部下の本音を引き出すどころか、逆に距離を広げてしまう要因となります。退職防止のために始めたはずが、実際には部下が「この会社では成長できない」と判断するきっかけになりかねません。
目的を再確認し、成長支援や信頼関係構築に重点を置くことが不可欠です。
上司の評価・指導ばかりで双方向性がない場合
1on1を「評価の場」と勘違いし、上司からの一方的なフィードバックや指導に終始してしまうケースも危険です。部下は「どうせ何を言っても聞いてもらえない」と感じ、自分の意見を出さなくなります。こうした状況では心理的安全性が失われ、1on1は本音を語る場ではなく「説教の時間」として受け止められてしまうのです。その結果、不満や悩みが蓄積し、退職という選択につながりやすくなります。
双方向性を意識し、部下の考えを尊重する姿勢を示すことが、信頼関係を築く第一歩です。質問を投げかけ、共感を示しながら会話を進めることが重要になります。
雑談だけで終わり、不満や課題が放置される場合
逆に、業務やキャリアに触れず雑談だけで終わる1on1も要注意です。一見フランクで話しやすい雰囲気を作れているように見えますが、課題解決やキャリア支援につながらないため、部下にとっては「意味のない時間」となりかねません。
特に退職を考えている社員は、深刻な悩みを抱えていても「どうせ聞いてもらえない」と諦め、退職を決断する可能性があります。雑談は関係構築に役立ちますが、それだけでは不十分です。毎回の1on1で「現状の課題」「今後のキャリア」「サポートしてほしいこと」など具体的なテーマを扱うことで、初めて退職防止につながる対話になります。
退職を防ぐための効果的な1on1の進め方
1on1を退職防止の仕組みとして機能させるには、単なる面談の繰り返しでは不十分です。部下の本音を引き出し、心理的安全性を高め、日々の成長を実感させる工夫が必要となります。さらに、キャリア志向を尊重することで「この会社で働き続けたい」という意欲を高めることが可能です。
ここでは、効果的な1on1の具体的な進め方を紹介します。
傾聴と共感を重視して本音を引き出す
1on1の最大の目的は、部下が安心して本音を語れる場をつくることです。そのためには、上司が「聞く姿勢」を徹底し、相手の言葉を遮らず最後まで受け止めることが欠かせません。さらに「それは大変だったね」「私も同じような経験があるよ」といった共感を示すことで、部下は「理解してもらえた」と感じやすくなります。
評価や指導に偏りすぎると防御的になり本音を隠してしまうため、まずは傾聴と共感を重視することが重要です。本音を引き出せれば、退職の兆候やモチベーション低下に早期対応でき、離職防止につながります。
定期的・高頻度で行い、関係性を深める
1on1は「やったら終わり」ではなく、定期的に継続することで効果を発揮します。
例えば月1回よりも週1回の方が、部下の変化や悩みをタイムリーに把握しやすく、信頼関係を強めることができます。特に若手社員は状況が変わりやすいため、短い時間でも高頻度で対話の場を持つことが有効です。継続することで「上司は自分を気にかけてくれている」という安心感が生まれ、エンゲージメントの向上にもつながります。
結果として、退職を考える前に相談してもらえる環境が整い、離職防止の効果を高めることができます。
承認や感謝を伝え、成長実感を与える
人が働き続けたいと感じる大きな理由のひとつは「自分の努力が認められている」という実感です。1on1では業務の進捗や成果だけでなく、日々の小さな工夫や努力を承認することが大切です。「ありがとう」「助かったよ」といった感謝の言葉を伝えることで、部下は承認欲求が満たされ、仕事へのモチベーションが高まります。
また、自分の成長を実感できれば「この会社でさらに成長できる」と思えるため、退職リスクは大きく減少します。単なる業務管理ではなく、承認と感謝を通じてエンゲージメントを高めることがポイントです。
キャリアの方向性や本人の希望を尊重する
1on1は、短期的な業務課題の解決だけでなく、部下のキャリア形成をサポートする場でもあります。「今後どんなスキルを磨きたいか」「どのような役割に挑戦したいか」といった本人の希望を尊重することで、会社で働き続ける理由が明確になります。逆にキャリア志向を無視すると「この会社にいても未来がない」と感じ、退職を選ぶリスクが高まります。
上司は会社の方針と部下の希望をすり合わせる役割を担うことが重要です。キャリア支援を通じて「この組織で成長できる」という安心感を与えることが、退職防止の最大の鍵となります。
実際の事例から学ぶ1on1と退職防止
1on1ミーティングの効果は理論だけでなく、実際の企業事例からも確認できます。導入によって退職率が大幅に減少した企業もあれば、運用を誤り逆効果となった失敗事例も存在します。また、ヤフーやサイバーエージェントといった先進的な企業の取り組みからは、多くの学びを得ることが可能です。
ここでは、それぞれの事例を具体的に解説します。
1on1導入で退職率が減少した企業の事例
あるIT企業では、若手社員の早期退職が課題となっていました。そこで導入したのが、週1回30分の1on1ミーティングです。
上司が傾聴を徹底し、業務の悩みだけでなくキャリアやプライベートの相談にも耳を傾けた結果、社員が「話を聞いてもらえる」という安心感を得られるようになりました。その結果、離職率は1年で30%以上改善し、エンゲージメントスコアも大幅に向上。
部下の本音を拾い上げ、課題が深刻化する前に解決できる仕組みが機能した好例です。1on1は適切に運用すれば、退職防止に直結する強力な人事施策となります。
1on1が逆効果となり離職を招いた失敗事例
一方で、形式だけ導入した結果、退職を招いた企業も存在します。
ある製造業では、月1回の1on1を義務化しましたが、上司が「評価の場」としてしか使わず、一方的な指導や説教に終始してしまいました。部下は「どうせ意見を言っても無駄」と感じ、本音を隠すようになり、最終的に数名の優秀な若手が短期間で退職する事態に発展しました。
このケースは、1on1が信頼関係を築く場ではなく「圧力の場」となった典型的な失敗例です。退職防止どころか逆効果にならないためには、上司への研修や目的の共有が不可欠です。
ヤフーやサイバーエージェントの取り組みから学ぶ
ヤフーやサイバーエージェントは、1on1を人材育成の基盤として成功させている代表的な企業です。ヤフーでは全社員を対象に1on1を定期的に実施し、キャリアの方向性や個々の強みを引き出す仕組みを整備。サイバーエージェントも「対話の場」としての1on1を重視し、若手社員の声を拾い上げることで定着率の向上に成功しています。
両社に共通するのは、単なる制度としての導入ではなく「文化」として根付かせている点です。このように先進企業の事例は、1on1を退職防止だけでなく人材育成や組織活性化につなげるヒントを与えてくれます。
まとめ|1on1を「退職防止」から「成長支援」の場へ
1on1ミーティングは、退職を未然に防ぐ有効な手段であると同時に、部下の成長を支援する大切な仕組みです。ただ離職を恐れるだけではなく、キャリア形成を後押しする視点を持つことで、社員のエンゲージメントを高められます。さらに、管理職自身のマネジメントのスキル向上や組織文化の改善も必要です。
最終的には「辞めさせない」ではなく「働き続けたい」と思える環境づくりにつなげることがとても大切です。
退職を恐れるだけでなく、部下のキャリア形成を支援する視点が重要
退職を防ぐことに意識が偏ると、1on1は「離職対策のための面談」となり、部下にとっては重苦しい場に感じられてしまいます。しかし、本来の目的は部下の成長やキャリア形成を支援することです。
部下が「ここで働きながら成長できる」と実感できれば、自然と退職リスクは下がります。キャリア相談やスキルアップの希望を聞き取り、具体的な機会を提供することで、働き続ける動機を強化できます。1on1を成長支援の場に位置づけることで、退職防止と人材育成の両立が可能になります。
継続的な改善と上司自身の成長が不可欠
効果的な1on1を続けるには、上司自身の成長も求められます。傾聴力や質問力、フィードバック力は一度学んで終わりではなく、実践を重ねて磨かれるものです。さらに、部下やチームからのフィードバックを受け入れ、面談の質を高める姿勢も大切です。
制度として1on1を導入するだけでは十分ではなく、実施方法を継続的に見直し、改善していくことで初めて効果が持続します。上司が学び続ける姿勢を見せることで、部下も「一緒に成長できる環境」と感じ、長期的な定着につながります。
「辞めさせない」より「働き続けたい」と思える環境づくりへ
退職防止を目的とするあまり「辞めさせないための1on1」となってしまうと、部下にとっては監視や引き止めのように感じられる危険があります。
本当に重要なのは、社員が「この会社で働き続けたい」と自然に思える環境づくりです。1on1を通じて不安や不満を解消し、承認や感謝を伝え、キャリア形成を支援することで、社員のモチベーションは高まります。
結果的に、退職防止は「目的」ではなく「成果」として実現されます。1on1を信頼と成長を育む場にすることこそ、持続的な組織づくりの鍵となります。ぜひこの記事を参考にした上で、1on1の面談に臨んでみてください。