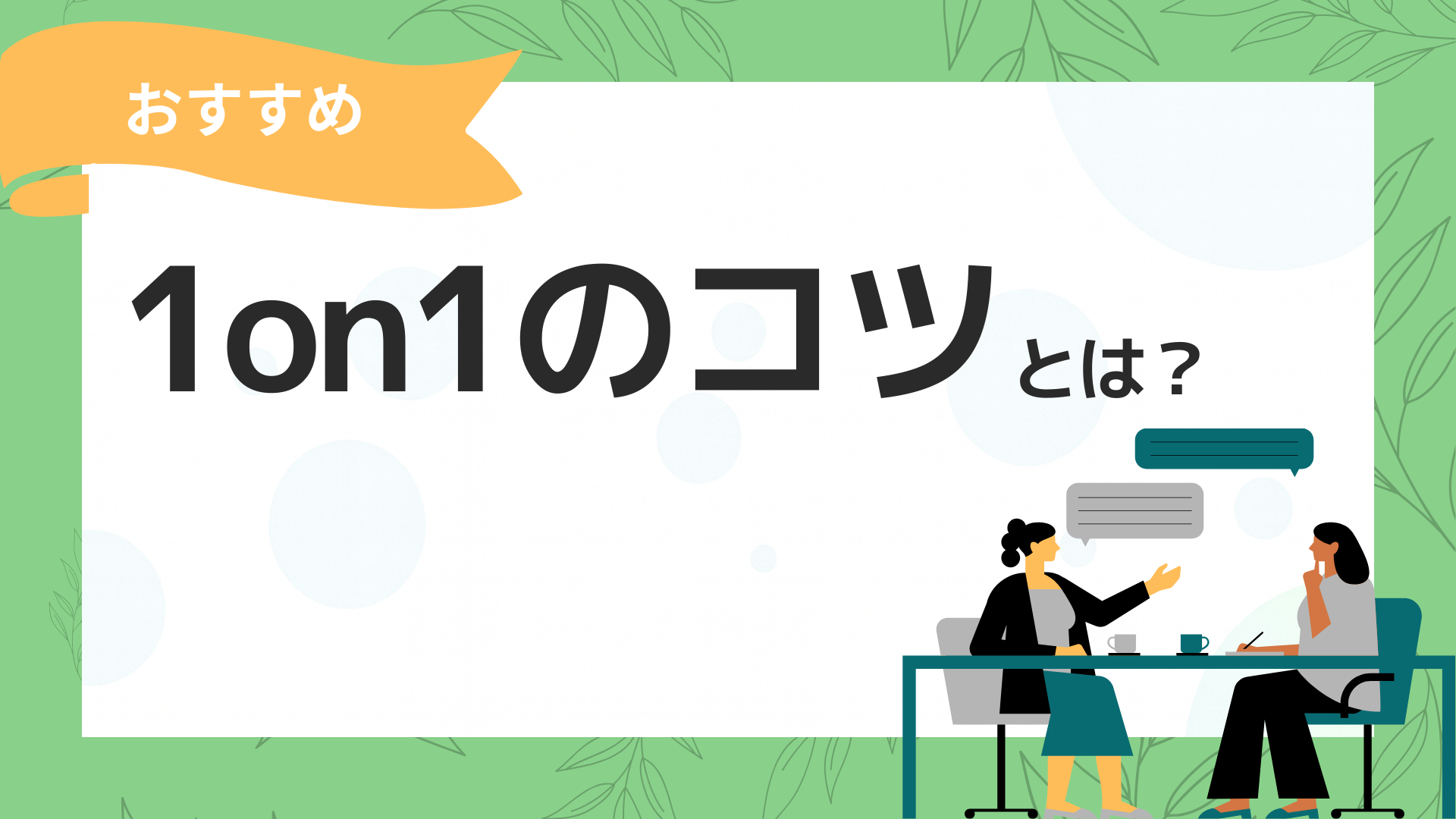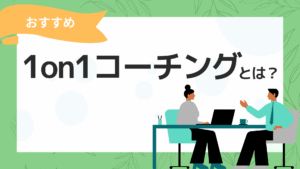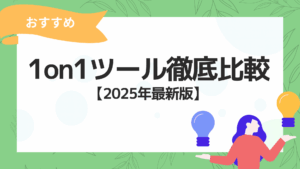1on1とは?その目的と注目される背景
近年、上司と部下が定期的に対話する「1on1ミーティング」が多くの企業で導入され、注目を集めています。従来の評価面談とは異なり、日常的なコミュニケーションの機会として活用されるのが1on1の特徴です。社員一人ひとりの思いや悩みに寄り添い、信頼関係を深めることで、組織全体の生産性やエンゲージメント向上につながるとして、多くの現場で重視されています。
では、具体的にどのような点が通常の面談と異なり、なぜ今このような取り組みが必要とされているのでしょうか。以下では、1on1の目的と注目される背景について解説します。
1on1と通常の面談との違い
1on1ミーティングと通常の面談の最大の違いは、「目的」と「頻度」にあります。
| 比較項目 | 1on1ミーティング | 通常の面談 |
| 目的 | 部下の成長、モチベーション向上、心理的安全性の確保 | 評価や業務報告が主目的 |
| コミュニケーション | 双方向の対話が前提、上司は「聞く」姿勢を重視 | 上司から部下への一方的なコミュニケーションに偏りがち |
| 頻度 | 月1回〜週1回など高い頻度で行われるのが一般的 | 不定期的、評価時期などに限定されることが多い |
| 機能 | 日常的なフォローや小さな気づきを積み重ねる場 | 定期的な評価や業績の確認の場 |
なぜ今、1on1が注目されているのか
1on1が注目されている背景には、以下の要因が挙げられます。
- 働き方の多様化とコミュニケーションの減少:リモートワークの普及などにより、社員同士のリアルなコミュニケーション機会が減少し、チームの一体感が薄れたり、上司と部下の関係が希薄になるなどの課題が浮き彫りになりました。1on1は、こうした状況下で信頼関係を再構築し、エンゲージメントを高める手段として注目されています。
- 多様な価値観への対応:Z世代やミレニアル世代など、キャリア志向や価値観が多様化する中で、個別に向き合う1on1は「自分を理解してもらえる」機会としても機能します。
- 組織力強化への貢献:心理的安全性を確保しながら、上司が部下を支援することで、離職率の低下や組織力の強化にもつながると期待されています。
1on1の効果とメリットとは
1on1ミーティングには、単なるコミュニケーションの場を超えた多くのメリットがあります。特に「信頼関係の構築」「部下の成長支援」「組織のエンゲージメント向上」といった面で効果が高く、定期的な対話によって上司と部下の関係性が強化されるのが特徴です。また、1on1のやり方や進め方に工夫を凝らすことで、業務改善や離職防止にもつながるといわれています。
以下では、1on1がもたらす具体的な効果について詳しく解説します。
信頼関係の構築とコミュニケーションの深化
1on1ミーティングの最大の効果の一つは、上司と部下の間に強固な信頼関係を築ける点です。
- 業務連絡や報告・連絡・相談(報連相)だけでは見えにくい「本音」や「感情」に触れる機会を設けることで、対話の質が向上します。
- 上司が傾聴の姿勢を持ち、部下の話を否定せずに受け止めることで、「安心して話せる場」が生まれ、心理的安全性が高まります。
こうした関係性は、日常業務の中でも自然なコミュニケーションの活性化につながり、トラブルや課題が表面化する前に対処できる組織づくりに役立ちます。
部下の成長とキャリア支援につながる
1on1は、部下の業務状況やスキルの把握だけでなく、キャリアビジョンの明確化や成長支援にも効果的です。
- 定期的な対話を通じて、目標の進捗や成功・失敗の振り返りを行うことで、自己認識力と課題解決力が高まる
- 上司が適切なフィードバックや問いかけを行うことで、部下が自身の成長プロセスを主体的に捉えるようになる
- 長期的なキャリア設計に関する対話を深めることで、社員の目標意識が強まり、離職リスクの低下にもつながる
1on1は、まさに人材育成の実践的なツールと言えるでしょう。
組織全体のエンゲージメント向上
個々の1on1が積み重なることで、組織全体のエンゲージメントが高まるという効果も見逃せません。
- 部下が「自分は大切にされている」と感じることで、仕事へのモチベーションや責任感が向上し、チーム全体の雰囲気にも好影響を与える
- 1on1を通じて現場の課題や改善点を吸い上げることで、マネジメント層が組織課題に対して迅速に対応できる体制が整う
結果的に、組織の風通しが良くなり、離職率の低下や生産性の向上といった成果にもつながるのです。効果的な1on1の実施は、企業全体の競争力を支える重要な施策として注目されています。
うまくいかない1on1のよくある課題
1on1ミーティングは、導入すれば自動的に成果が出るわけではありません。実際には、「なんとなく話して終わる」「続けられない」「意図が伝わらない」等、思うように効果を発揮できないケースも少なくありません。これらの失敗要因は、1on1の進め方や設計に課題があることが多く、事前の準備や運用ルールの見直しが求められます。
ここでは、特にありがちな3つの課題とその背景を解説し、改善のヒントを探ります。
雑談だけで終わってしまう
1on1ミーティングの本来の目的は、部下の成長支援や課題解決、キャリア形成などに向けた建設的な対話です。しかし、目的やアジェンダが定まっていないと、ただの雑談に終始してしまい、時間だけが過ぎてしまうというケースがよくあります。
雑談自体が悪いわけではなく、信頼関係を築く上で有効な面もありますが、それだけで終わってしまうと「意味のない時間だった」と部下に感じさせてしまう可能性があります。効果的な1on1を実現するには、雑談を入口にしつつも、業務や目標、成長に関する具体的な話題に移行する進行スキルが求められます。
目的が不明確なまま進めてしまう
1on1でよく見られる失敗は、ミーティングの「目的が曖昧なまま進んでしまう」ことです。
目的が共有されていないと、上司と部下の間に温度差が生まれ、ただ時間を消化するだけの形骸的な面談になりがちです。
例えば
「とりあえず話す」「最近どう?」といった曖昧な問いかけでは、部下もどう答えてよいか分からず、本質的な対話が生まれません。
1on1を効果的に進めるためには、「この回ではどんな話をしたいのか」「何をゴールにするのか」を事前に明確にしておくことが重要です。
事前に目的を設定・共有することで、会話の質が高まり、成果のある1on1に近づきます。
実施頻度が不安定・キャンセルが多い
1on1が継続的に実施されないことも、大きな課題の一つです。スケジュールの都合や多忙を理由に頻繁にキャンセルされたり、実施日がバラバラになると、部下にとっての信頼感や重要性が薄れ、「また中止になってしまうのではないか」といった形でモチベーションが下がってしまうこともあります。
1on1を形骸化させず、信頼される場として定着させるためには、「毎月第〇週の〇曜日」「必ず月に1回は実施」等といった、一定のルールを設けて継続することが大切です。
また、緊急時以外はリスケジュールしてでも実施するという姿勢が、部下へのリスペクトにもつながり、信頼関係の維持に直結します。
効果的な1on1の進め方【5つのステップ】
1on1ミーティングを成功させるには、事前の準備から実施後の振り返りまで、一連の流れを体系的に設計することが欠かせません。特に、目的の明確化・アジェンダ設定・傾聴・フィードバック・継続性の5つのステップが、効果的な進め方の基本となります。これらを意識することで、形だけの1on1を脱し、部下の成長支援や信頼関係の強化につながる充実した対話が実現できます。
この章では、各ステップのポイントを具体的に解説します。
Step1|目的とゴールを明確にする
1on1を開始する前に最も重要なのが、「何のために行うのか」という目的を明確にすることです。目的が曖昧なままでは、会話の軸が定まらず、効果的な対話にはつながりません。
- 「部下の成長支援」「現場の課題把握」「キャリア相談」など、ミーティングの主眼を共有しておくことで、上司と部下の間に認識のズレが生まれにくくなります。
- 目的に応じて毎回のゴールを設定することで、話題がぶれずに具体的かつ前向きな対話が可能になります。
1on1を形骸化させないためにも、「なぜこの対話をするのか」を両者で明確にすることが第一歩です。
Step2|アジェンダ・テーマを事前に決める
1on1をスムーズに進行するには、事前にアジェンダ(議題)やテーマを共有しておくことが効果的です。テーマが事前に決まっていれば、部下は話したいことを整理して臨めるため、会話の内容がより深まり、短時間でも有意義な対話が実現します。
アジェンダの例としては、
- 「今月の振り返り」
- 「困っている業務」
- 「今後のキャリアビジョン」等
具体性のあるテーマが好まれます。
また、部下自身にアジェンダ案を出してもらうことで、自発的な姿勢が育ち、1on1の主体性も高まります。準備が整っていれば、雑談だけで終わることを防ぎ、実のある1on1に繋がります。
Step3|傾聴と共感を重視した対話を行う
1on1の本質は、「上司が話す場」ではなく、「部下が安心して話せる場」をつくることにあります。そのために必要なのが、傾聴と共感の姿勢です。
- 話の途中で意見を挟んだり、結論を急いだりするのではなく、まずは相手の言葉にじっくり耳を傾けることが大切です。
- 特に、不安や悩みを打ち明ける場面では、否定や評価を控え、「そう感じたんだね」と共感的に受け止めることで、部下は安心して本音を語れるようになります。
上司の反応次第で1on1の空気感は大きく変わるため、言葉よりも「聴く力」が問われるフェーズだと心得ましょう。
Step4|記録とフィードバックで振り返る
1on1で話した内容を記録しておくことは、次回の対話や中長期的な成長支援において非常に有効です。
メモには、
- 話したトピック
- 部下の発言内容
- 上司からのアドバイス
- 次回までのアクション項目などを残すとよいでしょう。
また、1on1後のフォローアップとして、部下に簡単なフィードバックや励ましのメッセージを送ることで、「話を聞いてくれた」「気にかけてくれている」と感じてもらえ、信頼関係の深化につながります。記録とフィードバックをセットで行うことで、1on1の継続的な質の向上が期待できます。
Step5|継続的に実施し、改善を繰り返す
1on1は一度実施して終わるものではなく、定期的に継続することでその真価を発揮します。
- 月1回や隔週などの頻度を決めて習慣化することで、部下も「話す準備」がしやすくなり、1on1への期待や信頼感が高まります。
- 加えて、回を重ねるごとに「今回の1on1はどうだったか?」「もっと良くするには何が必要か?」といった振り返りを行い、進め方の改善を繰り返すことが重要です。
継続は信頼関係の構築力が強化され、改善は1on1の質の向上やさらなる人材育成にもつながります。1on1を「形式的な面談」ではなく「成長のための対話」として定着させるには、この両輪が欠かせません。
効果を高めるための具体的なコツと心構え
1on1ミーティングを真に効果的な場にするためには、形式にとらわれず「対話の質」を高める工夫と心構えが不可欠です。単なる報告・相談の時間にとどまらず、部下の気づきを引き出し、モチベーションや成長につなげるための関わり方を意識することが求められます。
特に重要なのが「問いかけ」「安心感」「自己開示」「育成の意識」という4つの観点です。ここでは、それぞれの具体的なコツと実践ポイントを詳しく解説します。
アドバイスより「気づき」を引き出す問いかけを
1on1では、上司が一方的にアドバイスを与えるのではなく、部下自身が考え、気づきを得られるような「問いかけ」が効果的です。
例えば、
- 「どうすればよかったと思う?」
- 「今のやり方にどんな工夫を加えられそう?」等
このような質問を投げかけることで、部下は自ら内省し、次のアクションを自律的に導き出せます。
これは「コーチング型1on1」とも呼ばれ、近年多くの企業が注目している手法です。アドバイス中心のコミュニケーションは、場合によっては部下の思考を止めてしまうリスクがあります。対話を通じて「自分で考える力」を育てることこそ、1on1が持つ大きな価値の一つです。
部下が話しやすくなる“安心感”をつくる
1on1で成果を出すためには、まず部下が「安心して話せる環境」を整えることが最優先です。心理的安全性が担保されていない場では、本音や悩みが出にくく、表面的な会話に終始してしまいます。
部下にとって「何を話しても否定されない」「評価されない場である」という信頼感があることが重要です。そのためには、上司が感情を抑えて傾聴する姿勢を見せたり、「今日は自由に話していいよ」といった言葉で安心感を伝えることが効果的です。
日頃の関係性の中で「この人には話しても大丈夫」と思ってもらえるような信頼の積み重ねが、質の高い1on1につながります。
上司自身も自己開示し、双方向の信頼を築く
1on1は、部下だけが話すのではなく、上司も必要に応じて「自己開示」することで対話の深まりが生まれます。上司が自らの過去の失敗や悩み、キャリアに関する価値観などを素直に語ることで、部下は共感しやすくなり、「この人も悩んでいたんだ」「正直に話していいんだ」と感じるようになります。
これは上下関係を超えた信頼の土台となり、部下の本音や課題が引き出しやすくなるのです。もちろん、自己開示の範囲やタイミングには注意が必要ですが、1on1を「対等な対話」として成立させるうえで、上司の柔軟な姿勢が信頼構築のカギを握ります。
1on1は「育成の場」であるという意識を持つ
多忙な業務の合間に行われる1on1は、つい義務的・形式的なミーティングになりがちです。しかし、1on1は単なる情報共有や現状報告の場ではなく、「人材育成の時間」として活用すべきものです。この意識が上司にあるかどうかで、対話の質が大きく変わります。
「この時間を通して、どんな成長を促したいか」「次の行動につながる気づきをどう引き出すか」といった観点を持つことで、1on1が有意義で戦略的な場になります。育成を意識することは、部下へのリスペクトの表れでもあり、上司としての信頼を高めるうえでも極めて重要な姿勢です。
1on1で話すべきテーマと質問例
1on1ミーティングでは「何を話せばよいか分からない」と悩む上司や部下も少なくありません。効果的な1on1にするためには、テーマ設定と問いかけの工夫が鍵を握ります。業務の進捗確認や課題の共有だけでなく、失敗体験の振り返りやメンタル面のフォロー、将来的なキャリアの方向性についても話題に取り入れることで、対話の幅が広がり信頼関係の構築にもつながります。
ここでは、1on1で押さえるべき代表的なテーマと、それぞれに適した質問例を紹介します。
業務の進捗や課題について
1on1で最も基本的かつ重要なテーマが、業務の進捗状況と課題の把握です。現状のタスクがどの程度進んでいるか、ボトルネックは何か、どんなサポートが必要かを共有することで、業務上の無駄やストレスを早期に発見できます。
質問例としては、
- 「今、最も時間を使っている仕事は?」
- 「スムーズに進んでいないことはある?」
- 「上司として手伝えることはある?」
定期的に進捗を確認することで、業務の方向性をすり合わせると同時に、部下の負担軽減や成果の最大化にもつながります。
成功・失敗体験とその振り返り
成功体験や失敗体験を振り返ることは、成長につながる重要な学びの機会です。1on1では、単なる結果報告ではなく、その背景にある判断・行動・思考プロセスに注目し、対話を深めることがポイントです。
質問例としては
- 「最近うまくいったことは何?」
- 「その時、どういう工夫をした?」
- 「反対に、うまくいかなかった場面は?」
- 「その経験から得たことは?」
このような問いかけをすることで、部下は自分の行動を客観視し、次の成長に活かす視点を持てるようになります。成功も失敗も、共有することで組織全体のナレッジとしても活用可能です。
メンタルや働き方への不安・体調確認
1on1は、業務の話だけでなく、メンタル面や働き方への不安、体調の変化などにも配慮できる貴重な場です。特にリモートワークや多忙な現場では、部下の心身の状態が見えづらくなっているため、このようなさりげない問いかけも大切です。
質問例としては
- 「最近、疲れていない?」
- 「休みは取れている?」
- 「何かストレスを感じていることは?」
話を聞くだけでも部下の安心感につながり、早期にメンタル不調を防ぐことができます。心理的安全性を高めるためにも、「評価の場ではない」という前提で、気軽に話せる雰囲気をつくることがポイントです。
キャリアビジョンや目標のすり合わせ
部下が将来的にどんなキャリアを望んでいるのか、どんな働き方をしたいのかを確認することも、1on1において重要なテーマです。上司がその意志を理解しておくことで、業務アサインや育成方針の調整がしやすくなり、離職防止にもつながります。
質問例としては
- 「今後やってみたい仕事はある?」
- 「どんなスキルを伸ばしたい?」
- 「5年後どうなっていたいと思う?」
こういった質問で、本人のビジョンを引き出しましょう。また、目標設定に対する進捗確認や、今の業務がどれだけキャリアにつながっているかを一緒に考えることも、モチベーション維持に効果的です。
まとめ
1on1ミーティングは、単なる面談ではなく、信頼関係の構築や部下の成長、組織全体のエンゲージメント向上につながる重要なコミュニケーション施策です。効果的に進めるためには、目的の明確化、アジェンダ設定、傾聴、フィードバック、継続実施といったステップを押さえることが不可欠です。
また、問いかけや自己開示による「対等な対話」の姿勢も、1on1を成功に導く鍵となります。テーマや話し方に悩んだ際は、本記事で紹介した質問例やコツや心構えを参考にし、日々の対話を改善していきましょう。1on1の質を高めることが、個人と組織の成長を支える第一歩です。