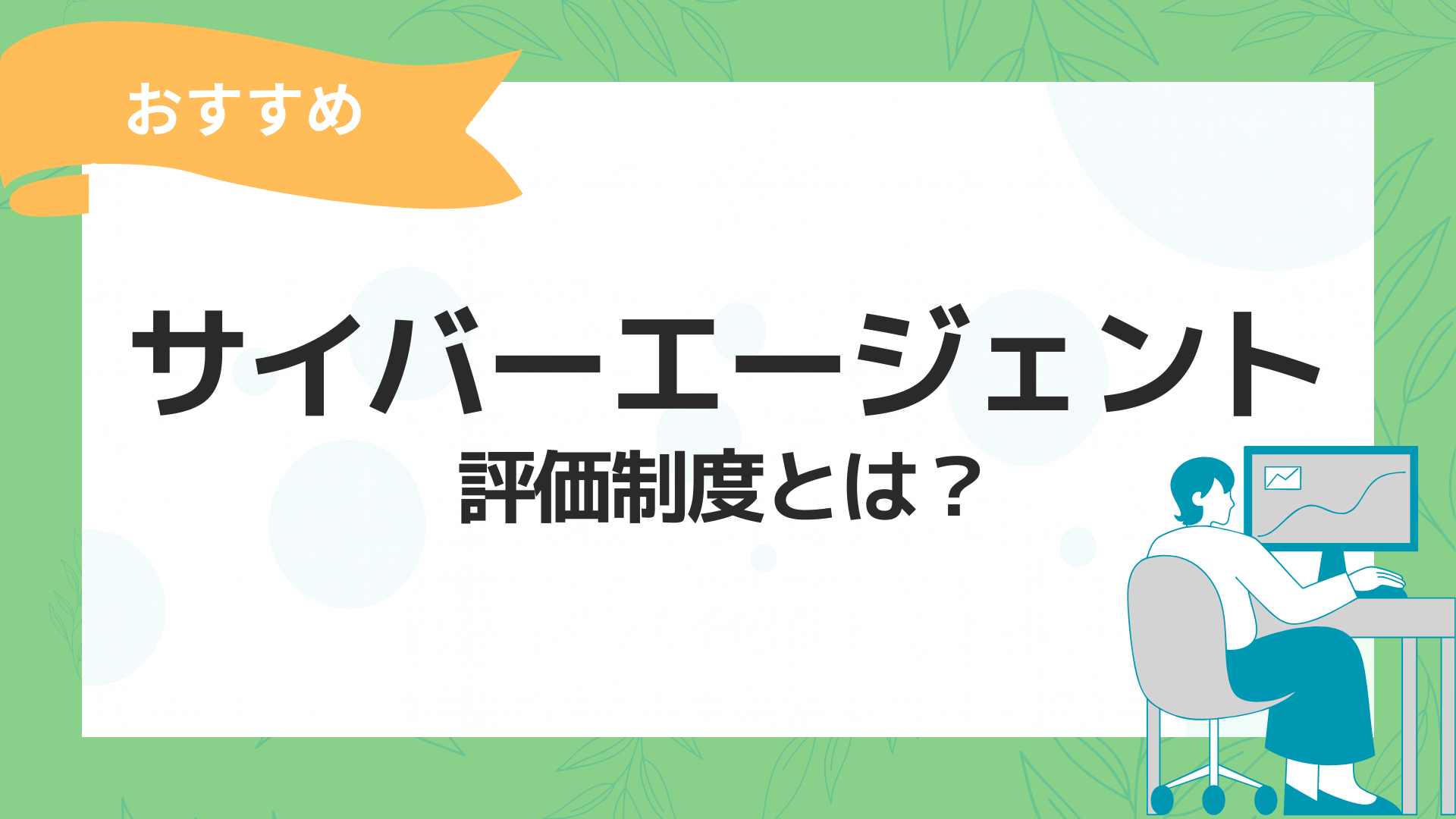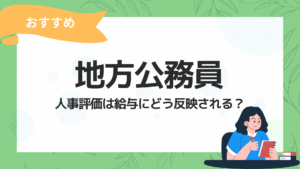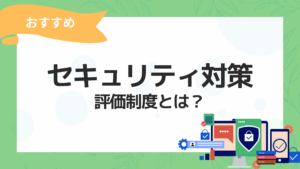サイバーエージェントの評価制度の概要
サイバーエージェントの評価制度は、従業員一人ひとりの成長と挑戦を重視しながら、成果を適切に評価する仕組みが整えられています。単なる人事評価にとどまらず、職務や職能の定義に基づいて役割を明確化し、社員が主体的にキャリアを描ける制度設計が特徴です。
また、従来の成果主義に偏るのではなく、挑戦を支援し人材育成につなげるスタイルへ進化している点が大きな魅力です。
以下では、サイバーエージェントの評価制度の概要について解説します。
評価制度の基本方針(職務・職能の考え方)
サイバーエージェントの評価制度の根幹には、職務(与えられた役割)と職能(発揮するスキルや能力)を明確に区分し、それぞれに応じて評価を行う仕組みがあります。これにより、成果だけではなく業務遂行に必要な能力や成長の度合いも正しく評価されるため、社員は自分の役割を理解しながらスキルアップを目指すことが可能です。
さらに、役職やポジションに関わらずフェアな基準で評価を行うことが意識されており、透明性の高い人事制度として社内に浸透しています。この職務・職能の考え方は、個々のキャリア形成を後押ししつつ、組織全体の成長に直結する仕組みになっているのが特徴です。
「成果主義」から「成長支援型」への進化
サイバーエージェントは創業期から成果主義を重視してきましたが、近年は「成長支援型」の評価制度へと大きくシフトしています。これは、短期的な成果だけで人材を評価すると、挑戦や学びが軽視されるリスクがあるためです。そこで同社は、挑戦の過程や成長プロセスを重視することで、失敗からも学べる環境を整えています。
例えば、新規事業提案制度「あした会議」やキャリアチャレンジ制度等、多様な取り組みを通じて社員が自己実現できる仕組みやサービスをを導入しています。成果と成長を両立させる評価方針は、社員のモチベーションを引き出し、変化の激しい業界で持続的に成果を出し続けるための基盤となっています。
評価を通じた人材育成・モチベーション向上の位置づけ
サイバーエージェントの評価制度は、人材育成とモチベーション向上を両立させる点に大きな特徴があります。評価結果は給与や昇進だけに反映されるのではなく、社員一人ひとりの強み・課題を明確にする「成長フィードバック」の機会として活用されています。
具体的には、月1回の面談や「GEPPO」と呼ばれるアンケート制度を通じて、社員のコンディションやキャリア志向を定期的に把握し、上司との対話を促進しています。これにより、社員は自分の努力が認められていると実感でき、前向きに次の挑戦へ取り組むことが可能になります。
評価を成長のサイクルに組み込む仕組みは、社員のエンゲージメントを高め、離職率の低下や組織力の強化につながっています。
具体的な評価制度・人材育成施策
サイバーエージェントの評価制度は、成果を測るだけではなく社員の挑戦や成長を後押しする仕組みが豊富に整えられています。
日常的な面談やトレーナー制度をはじめ、月1回のアンケートで社員の声を吸い上げる「GEPPO」、感情報酬を基盤とした「褒める文化」、さらに技術者支援制度「ENERGY」や価値観のズレを可視化するミスマッチ制度など、多面的なアプローチで社員のエンゲージメントを高めています。
ここでは、具体的な評価制度と人材育成施策について紹介します。
月イチ面談・トレーナー制度など日常的なフォロー
サイバーエージェントでは、社員の成長を日常的にサポートするために「月イチ面談」や「トレーナー制度」が導入されています。
- 月イチ面談:上司と部下が定期的に対話する場を設け、目標進捗や課題を共有しながら成長支援を行う仕組み
- トレーナー制度:新入社員や若手社員に経験豊富な先輩社員が付き、業務指導やキャリア相談に対応
これにより、社員は孤立することなく安心して成長できる環境が整えられ、早期戦力化と離職防止に効果を発揮しています。単なる評価の場ではなく、日常的なコミュニケーションがモチベーション維持につながっている点が特徴です。
独自制度「GEPPO」― 月1アンケートで社員の声を可視化
「GEPPO」は、サイバーエージェントが独自に開発した月1回の簡単なアンケート制度で、社員のコンディションやキャリア意識を可視化する仕組みです。
設問はシンプルながら、社員の満足度や悩みを把握でき、マネジメント層が早期に課題を発見・改善につなげることが可能になります。社員にとっても、自分の気持ちや状況を定期的に言語化する機会となり、組織全体の透明性が高まります。
実際にGEPPOを通じて、部署間異動やキャリア支援がスムーズに行われた事例も多く、社員の声を制度設計に活かす文化が根付いています。このように、評価とフィードバックを双方向に機能させる点がGEPPOの大きな特徴です。
感情報酬と「褒める文化」モチベーションを高める仕組み
サイバーエージェントの人材マネジメントにおいて大切にされているのが「感情報酬」です。
これは給与や役職といった金銭的・物理的報酬だけでなく、「承認」や「感謝」といった感情面での報酬を重視する考え方です。社員同士が積極的に褒め合う文化を育むことで、モチベーションを高め、組織の一体感を強化しています。
例えば、表彰制度や全社イベントでの成果共有、日常業務での小さな成功を称える仕組みが組み込まれています。感情報酬は、挑戦する姿勢やチームワークを評価対象に含めることで、成果だけでは測れない価値を見える化し、社員の自己肯定感を高める重要な役割を担っています。
技術者支援制度「ENERGY」開発・スキル・キャリア支援
技術者向けに設計された支援制度「ENERGY」は、サイバーエージェントのエンジニア人材育成を象徴する取り組みです。
ENERGYでは、開発支援・スキルアップ支援・キャリア支援という3つの柱を軸に、社員の専門性強化を後押ししています。
具体的には、
- 最新技術を活用できる開発環境の整備
- 社内外研修や勉強会の提供
- キャリア形成を支援する社内制度等が用意されている
さらに、社員の挑戦を奨励する風土の中で、エンジニアが安心して新しい技術に挑戦できる土壌が整っています。こうした施策は、単なる評価にとどまらず「長期的に働き続けられる環境づくり」としても高く評価されており、業界内でも先進的な取り組みの一つとされています。
「ミスマッチ制度」価値観のズレを早期に解消する仕組み
サイバーエージェントの評価制度の中でもユニークなのが「ミスマッチ制度」です。
これは、社員と会社の価値観が合わない場合に早期に対応する仕組みで、必要に応じて部署異動や退職勧奨が行われます。従来はマイナスな印象を持たれがちでしたが、同社はこれを「本人にとっても組織にとっても最適な選択」と位置づけています。
例えば、キャリア志向や働き方の不一致が早期に明らかになれば、社員は新しいフィールドで活躍するチャンスを得られますし、組織側も無理な配置による不満や生産性低下を防ぐことができます。
評価を「選別」ではなく「適材適所」の手段とすることで、全体のエンゲージメントを高める制度として機能している点が特徴です。
評価制度を支える組織文化と仕組み
サイバーエージェントの評価制度は、単なる人事考課にとどまらず、挑戦や成長を促す独自の組織文化に支えられています。
全社で未来を議論する「あした会議」や成果を称える「CyberAgent Award」、社員が自らキャリアを切り開く制度、人材科学センターによるデータ活用など、評価を組織風土に結びつけている点が特徴です。さらに役員交代や次世代マネジメント施策を通じて、変化に強いリーダーシップを育成し続けています。
ここでは、評価制度を支える組織文化の仕組みについてお伝えします。
あした会議・全社総会「CyberAgent Award」
「あした会議」は、サイバーエージェントの代表的な取り組みの一つで、役員や社員が集まり、新規事業や経営戦略を提案・議論する場です。この制度により、社員のアイデアや挑戦心が経営に直接反映される仕組みが構築されています。
また、全社総会で行われる「CyberAgent Award」では、部署単位や個人の成果を称え合う文化が根付いており、感情報酬を重視したモチベーション向上施策として機能しています。単なる表彰制度にとどまらず、評価を「挑戦する姿勢」や「チームの貢献」にも広げることで、社員が誇りを持って働ける組織づくりを支えています。
これらの取り組みは、会社全体の方向性を共有すると同時に、社員のエンゲージメントを高める役割を担っています。
キャリアチャレンジ制度(キャリチャレ・キャリバーなど)
サイバーエージェントでは、社員が自らの意思でキャリアを広げられるよう「キャリチャレ」や「キャリバー」といったキャリアチャレンジ制度を整えています。
- キャリチャレ:社内公募に応じて新しい部署やプロジェクトへ挑戦できる仕組みで、社員の自主的な成長を後押し
- キャリバー:中長期的なキャリア形成を支援する制度で、キャリア相談やスキル開発の機会が提供される
これらの制度は、社員が「やりたいこと」を追求できる環境を整えると同時に、会社としても多様な人材の可能性を最大限に引き出す仕組みとなっています。成果だけでなく「挑戦する姿勢」を評価の対象とすることで、社員のキャリア選択に柔軟性を持たせ、長期的な成長と組織の活性化を実現しています。
人材科学センターによるデータ活用
サイバーエージェントは、人事評価をより客観的かつ精緻に行うために「人材科学センター」を設立しています。この組織では、社員の働き方やモチベーション、評価データを収集・分析し、人材マネジメントに活用しています。
例えば、GEPPOで得られたアンケート情報や人事データを統合的に分析し、適切な配置やキャリア支援に反映させる取り組みが進められています。これにより、属人的な判断に頼らず、データに基づいた公平性の高い評価が実現されています。
また、社員にとっても「評価の透明性」が高まり、納得感を持って成長に取り組める環境が整っています。データドリブンな評価運用は、離職率低下や適材適所の人材配置といった成果にもつながっており、他社との差別化要因になっています。
役員交代制度・次世代マネジメント施策
サイバーエージェントの独自施策として注目されるのが「役員交代制度」です。これは、一定期間ごとに役員を入れ替える仕組みで、次世代リーダーに経営経験を積ませることを目的としています。若手社員にも経営に関わるチャンスが巡ってくるため、組織全体に挑戦意識と当事者意識を浸透させる効果があります。
さらに「次世代マネジメント室」などの取り組みを通じて、未来の経営人材を計画的に育成しています。これらの制度は、変化の激しいIT・インターネット業界で持続的に成果を上げるための仕組みであり、評価制度と連動して社員のキャリア形成を後押ししています。
役員交代による組織の新陳代謝は、停滞を防ぎ、新しい発想や視点を取り入れる柔軟な企業文化を維持するための大きな特徴といえます。
社員から見た評価制度の評判・口コミ
サイバーエージェントの評価制度は、多様な制度や仕組みが整備されている一方で、社員の受け止め方には肯定的な意見と課題の双方があります。成長を促す仕組みや挑戦を後押しする文化は高く評価される一方で、成果に対するプレッシャーや長時間労働への懸念も見られます。また、給与や昇進に直結する評価の透明性についても、意見が分かれる点が特徴です。
ここでは、社員から見た評価制度についての評判を紹介します。
成長や挑戦を後押しする点での高評価
多くの社員から高く評価されているのは、挑戦を歓迎する文化とそれを支える制度設計です。
新規事業提案やキャリアチャレンジ制度、GEPPO等、社員が自らの意志でキャリアを切り拓ける仕組みが整っており、成長機会に恵まれている点がポジティブに捉えられています。特に若手社員でも裁量を与えられ、経営に近い業務や責任あるポジションを早期に経験できることが魅力とされています。
これにより、個々の挑戦が評価につながりやすく、自己実現を後押しする環境が整っていると感じる社員が多いのが特徴です。挑戦を評価に結びつける姿勢は、社員のモチベーション維持や組織の活性化に寄与しています。
成果へのプレッシャーとハードワーク文化の課題
一方で、成果主義を基盤とする文化は社員に強いプレッシャーを与える側面もあります。
成長機会が豊富にある反面、常に高い成果を求められるため、長時間労働や精神的な負荷が課題として指摘されています。口コミの中には「結果を出せば評価されるが、出せなければ厳しい環境」との声もあり、成果への強い期待がモチベーションに作用する一方で、燃え尽きや離職につながる可能性も否定できません。
サイバーエージェントは「成長支援型」への制度転換を進めていますが、現場レベルでは依然として成果重視の文化が根強く、社員の受け止め方には温度差があるのが実情です。挑戦と成果のバランスをどう取るかが今後の課題といえます。
給与・昇進における評価の透明性に関する意見
給与や昇進に直結する評価の透明性については、社員の間で意見が分かれています。
評価制度の仕組み自体は整備されており、面談やフィードバックの機会もあるものの、実際にどのような基準で昇進や給与決定が行われているのか、十分に理解できていないと感じる声もあります。
一方で、上司とのコミュニケーションを通じて納得感を得ている社員もおり、マネジメントの裁量やコミュニケーション力によって評価の受け止め方に差が出ているのが現状です。
制度としては公平性を重視していますが、現場での運用にばらつきがあることが、評価に対する透明性の課題として浮き彫りになっています。
他社と比較したサイバーエージェントの特徴
サイバーエージェントの評価制度は、他社の人事制度と比べても独自性が際立っています。最大の特徴は、制度を常に見直し更新し続ける柔軟さにあります。さらに、社員個人の成長と組織全体の成果を同時に評価するバランス感覚や、テック人材やクリエイター人材への支援制度が充実している点も注目されます。これらの特徴は、変化の激しいIT・インターネット業界で競争力を維持する上で大きな強みとなっています。
ここでは、他社と比較したサイバーエージェントの特徴を解説します。
制度を「更新し続ける」柔軟さ
サイバーエージェントの評価制度の最大の特徴は、環境変化に応じて常に制度をアップデートし続ける柔軟さです。成果主義から成長支援型への転換や、役員交代制度、GEPPOなどの導入は、時代や社員ニーズに合わせて進化してきた象徴的な事例です。
多くの企業では評価制度が固定化され、形骸化するリスクがありますが、同社は制度を「絶えず改善する仕組み」として捉えており、その柔軟性が社員の納得感を高めています。こうした制度の更新サイクルは、変化が速いIT業界に適応するために不可欠であり、サイバーエージェントが長期にわたり人材を引きつける要因の一つとなっています。
個人の成長と組織成果を両立させる評価軸
サイバーエージェントの評価制度は、成果だけでなく個人の成長プロセスも重視する点で他社と一線を画しています。
評価の軸は「組織への貢献度」と「個人の成長度合い」に置かれ、挑戦や学習の姿勢も評価対象となります。この仕組みにより、短期的な成果にとらわれず、中長期的な人材育成を可能にしています。
例えば、新規事業提案やキャリアチャレンジ制度を通じて挑戦を奨励し、その過程を正当に評価する仕組みは、社員のモチベーション向上につながっています。成果と成長の両立を制度として設計している点は、多くの企業が導入を模索する中で、すでに先進的に実践している事例といえるでしょう。
テック人材・クリエイター人材への手厚い支援
サイバーエージェントは、特にテック人材やクリエイター人材への支援制度が充実している点でも特徴的です。
エンジニア向けには「ENERGY」と呼ばれる開発・スキル・キャリア支援制度を用意し、最新技術の習得や長期的なキャリア形成をサポートしています。また、クリエイターやデザイナー向けにも、発想力や表現力を高める研修や評価指標を整備し、成果と創造性を両立できる仕組みを導入しています。
他社では成果を数値化しづらい職種の評価が課題になりがちですが、サイバーエージェントは専門職に合わせた評価軸を柔軟に取り入れることで、社員の能力を最大限に引き出しています。この手厚い支援が、優秀な人材の獲得と定着に大きく寄与しています。
まとめ|サイバーエージェントに学ぶ評価制度のポイント
サイバーエージェントの評価制度は、成長と成果を両立させるユニークな仕組みとして注目されています。人材育成を重視した制度運用、感情報酬を取り入れたモチベーション施策、さらに制度を常に見直し進化させる柔軟さが特徴です。他社にとっても、自社の評価制度を見直す際の参考となるポイントが数多く含まれています。
ここでは、サイバーエージェントに学ぶ評価制度のポイントを3つ紹介します。
人材育成とモチベーションを高める仕組みづくり
サイバーエージェントの評価制度から学べる第一のポイントは、人材育成とモチベーションを両立させる仕組みを制度に組み込んでいることです。
月イチ面談やGEPPOを通じて社員の声を拾い、日常的にフィードバックを行う仕組みは、社員が「成長実感」を得られる大きな要因になっています。さらに感情報酬を重視し、成果だけでなく挑戦する姿勢や貢献も評価対象に含めることで、組織全体に前向きな雰囲気を浸透させています。
このように、評価制度を単なる人事査定の枠にとどめず、社員の成長を促す仕掛けとして活用する姿勢は、持続的な人材育成とエンゲージメント向上につながっています。
成果主義に偏らない制度設計の重要性
次に注目すべきは、成果主義に偏らない制度設計の重要性です。
サイバーエージェントは創業期こそ成果重視の文化を持っていましたが、現在は挑戦の過程や成長プロセスを評価に取り入れる「成長支援型」へと進化しています。成果だけを基準とすると短期的な評価に偏りやすく、社員の挑戦や新しい発想を阻害するリスクがあります。そのため、失敗も成長の一部と捉える制度設計が不可欠です。
社員が安心して挑戦できる環境を提供することは、長期的に優秀な人材を育成し、組織の持続的な競争力を高めるための大切なポイントといえるでしょう。
変化に合わせて制度をアップデートする姿勢
最後に、サイバーエージェントの制度運用から学べるのは「常に制度を進化させる姿勢」です。
同社は、役員交代制度や新規事業提案制度などを時代や環境に応じて柔軟に更新しており、制度が形骸化しないよう工夫されています。この姿勢は、変化の激しいインターネット業界で成果を出し続けるための重要な要素であり、他社の人事制度改革にも参考になります。
評価制度は一度作れば終わりではなく、環境変化や社員ニーズに合わせて調整・改善を重ねることで、本来の目的である「社員の成長と組織の発展」を実現できます。サイバーエージェントの事例は、制度を常にアップデートする柔軟性の価値を示しています。
ぜひ具体的な評価制度についても本記事を参考にしてみてください。